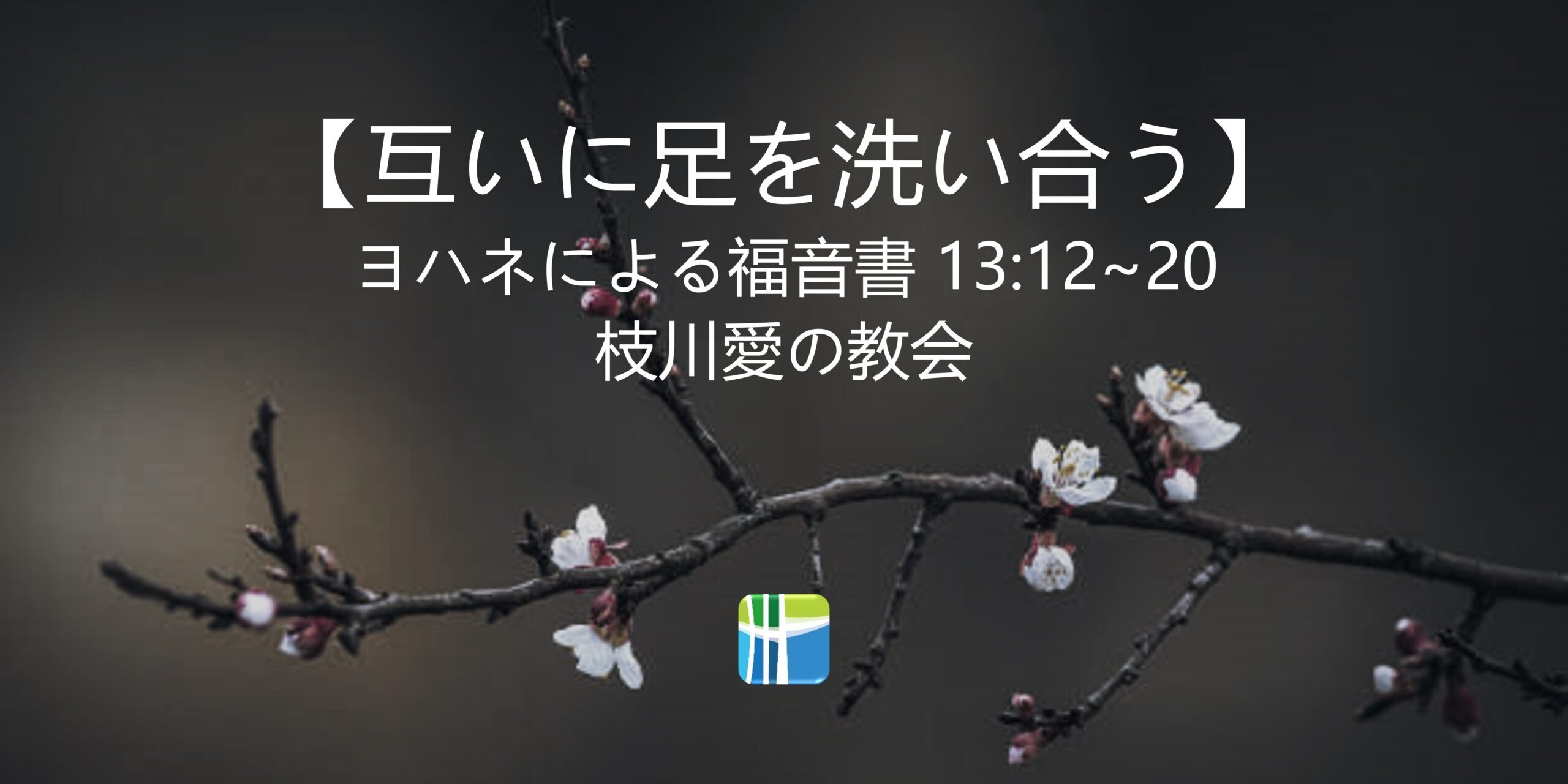ヨハネによる福音書 13:12~20
13:12 イエスは彼らの足を洗うと、上着を着て再び席に着き、彼らに言われた。「わたしがあなたがたに何をしたのか分かりますか。
13:13 あなたがたはわたしを『先生』とか『主』とか呼んでいます。そう言うのは正しいことです。そのとおりなのですから。
13:14 主であり、師であるこのわたしが、あなたがたの足を洗ったのであれば、あなたがたもまた、互いに足を洗い合わなければなりません。
13:15 わたしがあなたがたにしたとおりに、あなたがたもするようにと、あなたがたに模範を示したのです。
13:16 まことに、まことに、あなたがたに言います。しもべは主人にまさらず、遣わされた者は遣わした者にまさりません。
13:17 これらのことが分かっているなら、そして、それを行うなら、あなたがたは幸いです。
13:18 わたしは、あなたがたすべてについて言っているのではありません。わたしは、自分が選んだ者たちを知っています。けれども、聖書に『わたしのパンを食べている者が、わたしに向かって、かかとを上げます』と書いてあることは成就するのです。
13:19 事が起こる前に、今からあなたがたに言っておきます。起こったときに、わたしが『わたしはある』であることを、あなたがたが信じるためです。
13:20 まことに、まことに、あなたがたに言います。わたしが遣わす者を受け入れる者は、わたしを受け入れるのです。そして、わたしを受け入れる者は、わたしを遣わされた方を受け入れるのです。」
古代中東では、サンダルのような履物を履いており、土ぼこりで足が汚れると、家に入る前に足を洗わなければなりませんでした。奴隷制度があった時代、主人の足を洗うことは奴隷の役割でした。客を迎える際に足を洗ってあげることは歓待の意味を持ち、奴隷を使う家庭では奴隷が主人や客の足を洗いました。
ところが、イエス様は弟子たちの足を洗われました。それは弟子たちにとって、受け入れ難いほどの畏れ多いことでした。洗足が終わった後、イエス様はその意味を語られ、弟子たちに互いの足を洗うようにと命じられました。奴隷がすべきことをイエス様ご自身が模範として行われたのですから、互いに足を洗うようにという命令に、誰も異議を唱えることはできませんでした。
教会では、洗足式は珍しくありません。仕える決意を込めて、牧師が聖徒の足を洗うこともあれば、教会学校の教師が子どもたちの足を洗うこともあります。そのたびに、謙虚に自らを低くし、他者に仕える決意が新たになります。足を触れ、洗ってあげることは、謙遜であり、尊重であり、親しさの表れです。
しかし、それはあくまで儀式であり、イベントです。一年に一度の洗足式では、「足が汚くて洗えない」と言う人はいませんが、「あの人が嫌だからこの教会にはもう来たくない」と言う人は数え切れないほどいます。洗足式はできても、兄弟の憎しみを洗い流すことは難しいのです。
聖餐式が、単に物理的な意味でパンとぶどう酒を食べることではなく、キリストの血と肉が聖徒の体の中で結びつく化学的な作用であるならば、洗足式は水で兄弟の足を洗う物理的な洗浄ではなく、赦しと受け入れによって互いを包み込む関係の浄化を意味します。あの人を受け入れ、抱きしめることができない洗足式は、無意味なのです。
韓国語では、悪い行いをやめることを「手を洗う」と言いますが、日本語では「足を洗う」と表現します。争いをやめ、互いの足を洗って対立や分裂から「足を洗う」べきではないでしょうか?いわゆる保守と進歩に分かれて争うキリスト教徒たちが、キリストの教えに従って広場にたらいを持ち寄り、洗足式をしてみるのはどうでしょうか?