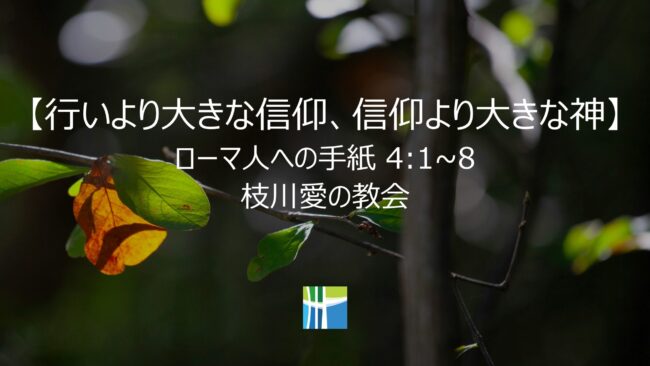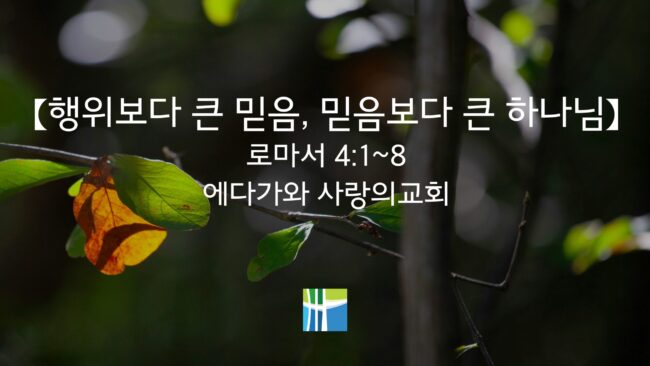ローマ人への手紙 黙想 【行いより大きな信仰、信仰より大きな神】 20250909 (火) 枝川愛の教会 趙鏞吉 牧師
ローマ人への手紙 4:1~8 4:1 それでは、肉による私たちの父祖アブラハムは何を見出した、と言えるのでしょうか。 4:2 もしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができます。しかし、神の御前ではそうではありません。 4:3 聖書は何と言っていますか。「アブラハムは神を信じた。それで、それが彼の義と認められた」とあります。 4:4 働く者にとっては、報酬は恵みによるものではなく、当然支払われるべきものと見なされます。 4:5 しかし、働きがない人であっても、不敬虔な者を義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。 4:6 同じようにダビデも、行いと関わりなく、神が義とお認めになる人の幸いを、このように言っています。 4:7 「幸いなことよ、不法を赦され、罪をおおわれた人たち。 4:8 幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人。」 ローマ人への手紙3章で、パウロはすべての人が罪のもとにあることを明らかにし、律法の行いによっては義と認められることができず、ただイエス・キリストを信じる信仰によって義とされるのだと語った。この宣言は当時のユダヤ人には耳慣れないものであり、パウロが律法を否定したり、新しい思想を唱えていると誤解される可能性もあった。そこでパウロは、ユダヤ人にとって最も信頼される象徴であるアブラハムを呼び出す。ユダヤ人が祖と仰ぎ誇りとしていたアブラハムさえも、実は行いではなく信仰によって義と認められたのだという事実を思い起こさせようとするのである。パウロは、いかなる場合においても、神の恵みとそれを信じる信仰に基づいた義認だけが神の方法であると語ろうとしているのである。だからこそパウロは、アブラハムとダビデを引き合いに出し、信仰によって得られる義と罪の赦しの幸い、すなわち神から始まった恵みについて語っているのである。 アブラハムがアブラハムとなり得たのは、能力や努力のおかげではなかった。いわゆる「信仰が強かった」からでもなかった。人々が「信仰深い」と言うときのその信仰ではなかった。アブラハムは最初から最後まで、神の召しに導かれて生きた。歯を食いしばって献身したのでもなく、信仰が強かったから従ったのでもなかった。ただ、それ以外は見えなかったからである。だからこそ、恵みなのだ。人々の目には難しく、立派に見えたかもしれないが、アブラハム自身にとっては苦しいことではなかっただろう。他のものは見えなかったからである。パウロは律法ではなく信仰だと言っているが、その信仰さえもアブラハムがひねり出したものではなかった。すべては、神がアブラハムを召し、支えられた恵みによって可能になったのである。 アブラハムの生涯は部分的な成就で終わった。空の星のような子孫の代わりにイサク一人を得ただけであり、カナンの地の嗣業の代わりに墓穴ひとつを所有したにすぎなかった。その未完成の中にあっても、アブラハムはなおその道を歩み続けた。疑わないことが信仰なのではなく、その道を最後まで歩むことこそが信仰である。自分の空間と時間を超えて、神が成し遂げられる約束に捕らえられて生きることである。アブラハムが恐れの中で揺れ動き、待つ中で過ちを犯したときでさえ、神は彼を見捨てられなかった。信仰とは、完全な人の力ではなく、弱き者を支えられる神の恵みの出来事である。 これを何と呼べばよいだろうか。アブラハムとダビデは誰よりも激しい信仰と従順の生涯を生きた人々であったが、それらすべてが神の恵みであったことを語らざるを得ない証言で終わる。逆に、自分は信仰が強いからその信仰によって何かができると思っている人は、アブラハムの人生も、ダビデの証言も、パウロの訴えも理解できないだろう。パウロは律法ではなく恵み、行いではなく信仰について語っているが、それはすなわち「私」ではなく「神」について語っているのである。歴史の中で問題を引き起こしてきたのは、信仰のない人々ではなく、自分は信仰が強いとうぬぼれる人々であった。肩や首に入った力を抜き、自分の位置と関係を告白しなければならない。神の召しと導きは、いつでも私の信仰と従順よりも大きいのである。