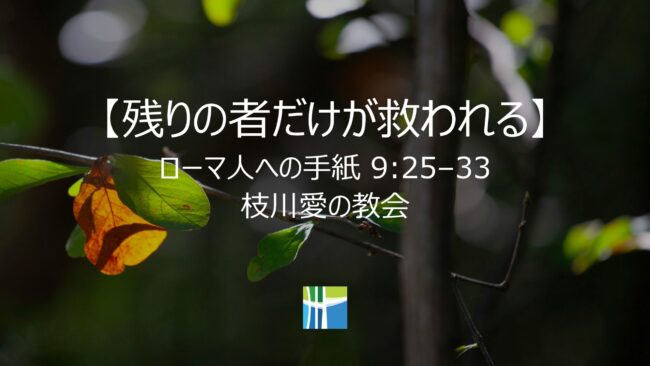ローマ人への手紙 黙想 【残りの者だけが救われる】 20250925 (木) 枝川愛の教会 趙鏞吉 牧師
ローマ人への手紙 9:25–33 9:25 それは、ホセアの書でも神が言っておられるとおりです。「わたしは、わたしの民でない者をわたしの民と呼び、愛されない者を愛される者と呼ぶ。 9:26 あなたがたはわたしの民ではない、と言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと呼ばれる。」 9:27 イザヤはイスラエルについてこう叫んでいます。「たとえ、イスラエルの子らの数が海の砂のようであっても、残りの者だけが救われる。 9:28 主が、語られたことを完全に、かつ速やかに、地の上で行おうとしておられる。」 9:29 また、イザヤがあらかじめ告げたとおりです。「もしも、万軍の主が、私たちに子孫を残されなかったなら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていたであろう。」 9:30 それでは、どのように言うべきでしょうか。義を追い求めなかった異邦人が義を、すなわち、信仰による義を得ました。 9:31 しかし、イスラエルは、義の律法を追い求めていたのに、その律法に到達しませんでした。 9:32 なぜでしょうか。信仰によってではなく、行いによるかのように追い求めたからです。彼らは、つまずきの石につまずいたのです。 9:33 「見よ、わたしはシオンに、つまずきの石、妨げの岩を置く。この方に信頼する者は失望させられることがない」と書いてあるとおりです。 パウロは、救いが民族的特権や血統によるのではなく、全く神の恵みと憐れみ、そして主権にかかっていることを明らかにした。それはユダヤ人を排除する論理ではなく、異邦人を受け入れる論理であった。救いはイスラエルという境界の中に閉じ込められてはいない。ホセアとイザヤを通して、神は「わたしの民でなかった者をわたしの民と呼び」、「愛されなかった者を愛される者と呼ばれた」。これは異邦人へと開かれた普遍的な福音の地平を示している。パウロの一貫した主題と核心は、神の救いがユダヤにとどまらないという宣教の拡張である。救いをキリスト教的規範の内に限定しようとすることは、律法主義が繰り返してきた過ちである。神の救いを妨げることのできるいかなるバリケードも存在しない。 救いの条件は所属や行為ではない。ただ信仰のみである。「ただ」という言葉は、行為や律法が排除されることを意味すると同時に、他のいかなるものとも混ざり合わない純粋な状態を指す。「ただ信仰」の状態を持ったことがあるかどうか、私たちは問わなければならない。「ただ聖書」(Sola Scriptura)、すなわち御言葉に支配されない人は「ただ信仰」(Sola Fide)を経験したことのない人である。イザヤは、イスラエルの数が海の砂のように多くても、残された者だけが救われると警告した。救いにおいて多数であることは保証にならない。むしろ多数は盲目的な群衆となる可能性が大きい。救いは血統的イスラエル、すなわち宗教的所属ではなく、信仰によって残る者にのみ与えられる。ゆえに信仰とは集団的なものではなく、主体は集団ではなく個人である。聖徒は自らの信仰について人格的責任を負わなければならず、集団的言語の中に隠れて抽象的な信仰を告白していないか省察しなければならない。 パウロは律法学者らしく、旧約全体を通して福音を示している。福音の中で御言葉は新たに鮮明となった。これこそがパウロの情熱であった。彼は異邦人とイスラエルを対比した。義を追い求めなかった異邦人は信仰によって義を得たが、律法に没頭していたイスラエルはかえって律法に到達できなかった。救いは努力の結果ではなく、ただ信仰による恵みの賜物である。信仰を再定義し更新しない者の終わりは、必ず形式主義と律法主義である。自ら生きようとする者は生きることができず、律法を守ろうとする者は律法を守り通すことができない。人間を理解しない者は救いを理解することもできない。しかし、自らの壊れを認め、信仰によって生きるとは何かを深く思い悩む者は、ついには救いに至らせる信仰を悟るのである。