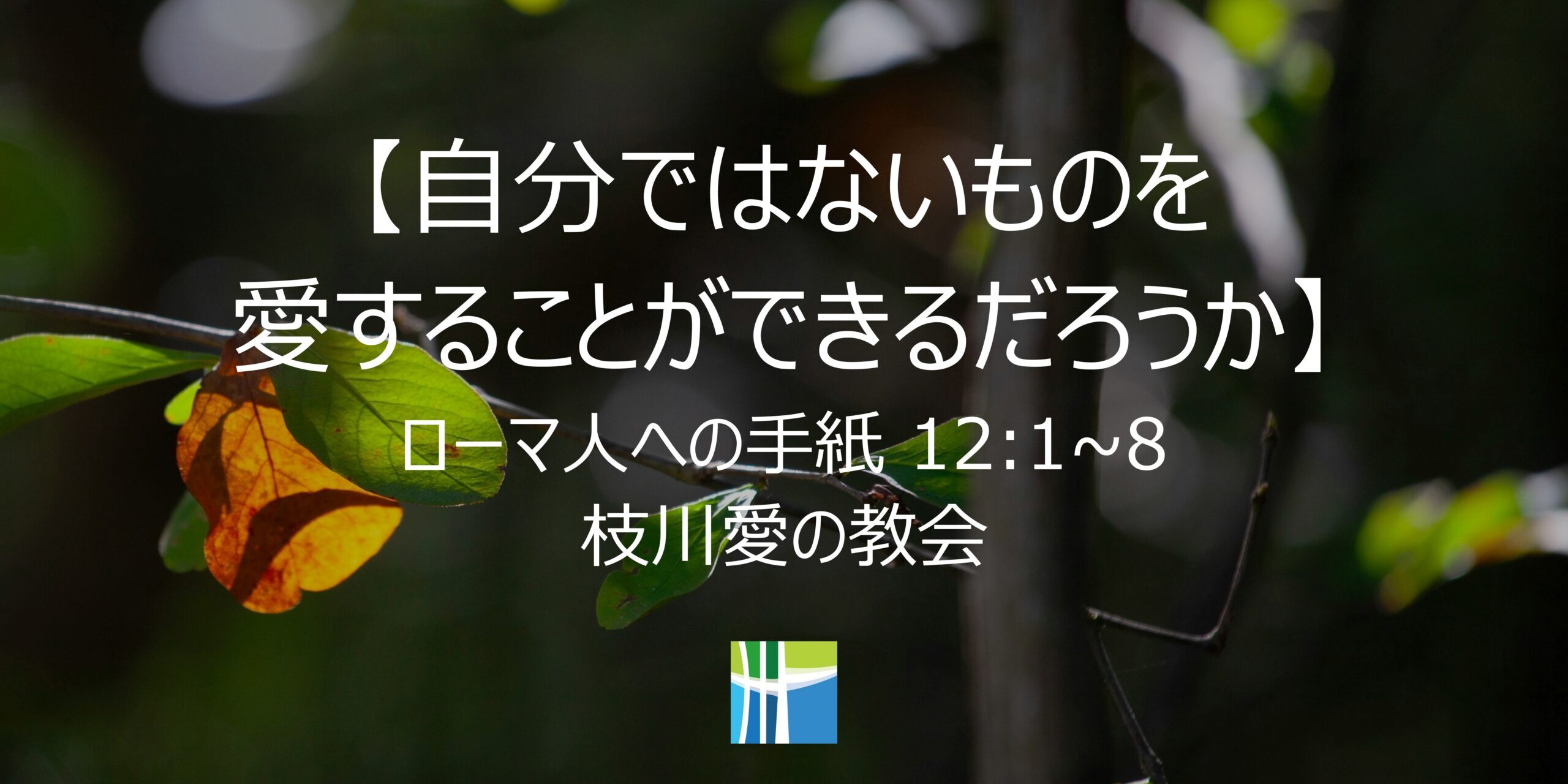ローマ人への手紙 12:9~14
12:9 愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れないようにしなさい。
12:10 兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手をすぐれた者として尊敬し合いなさい。
12:11 勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。
12:12 望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。
12:13 聖徒たちの必要をともに満たし、努めて人をもてなしなさい。
12:14 あなたがたを迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって、呪ってはいけません。
誰もが本能的に自分を中心に考え、自分を基準にして他者を評価する。だから「自分を愛してこそ他人も愛せる」という言葉をよく耳にする。まず自分を満たし、そのあふれた分で他者に向かえばよいと言うのだ。それは間違いとは言えないが、愛の供給者を自分自身だと思っている人々の話にすぎない。自己愛を越えられない人にとって、愛は始まりすらしない。では、私たちは自分ではない存在を愛することができるのだろうか。
パウロは救いの核心を長く語った後、具体的な生活の態度へと導いている。最初の主題は「献身」であり、その次に必然的に伴うものとして「愛」が語られる。「悪を憎み、善に従え。兄弟を愛し、互いに尊敬することを先にせよ。怠けず、心に熱意を抱き、主に仕えよ。希望のうちに喜び、苦難のうちに耐え、祈りに励め。聖徒の必要を満たし、もてなしを熱心にせよ。さらに迫害する者をも祝福せよ。」
パウロが提示する愛の言葉はすべて、自分中心を否定し、他者へと向かう動詞である。愛が名詞であるとき、それは概念となり、よく見えるが手に取れず、言葉だけの観念にすぎない。しかし動詞であるとき、それは出来事となる。赦しとなり、分かち合いとなり、尊敬となり、歓待となる。その瞬間、愛は生きて動く実在となるのだ。
敵を祝福し、迫害する者のために祈ることは、人間の本能では不可能である。パウロはその反論を受けるつもりがなかったからこそ、先にキリストの福音を語ったのだ。愛はすでにそこにあるからである。私が自分ではない神に愛されていると信じるとき、私は自分ではない誰かを愛することができるだろう。この議論に律法が入り込む余地はない。たとえ今持っているものを愛と呼ぶには及ばないとしても、与えられた人生がその方向に向かっていると信じること、それを信仰と呼ぶべきだろう。