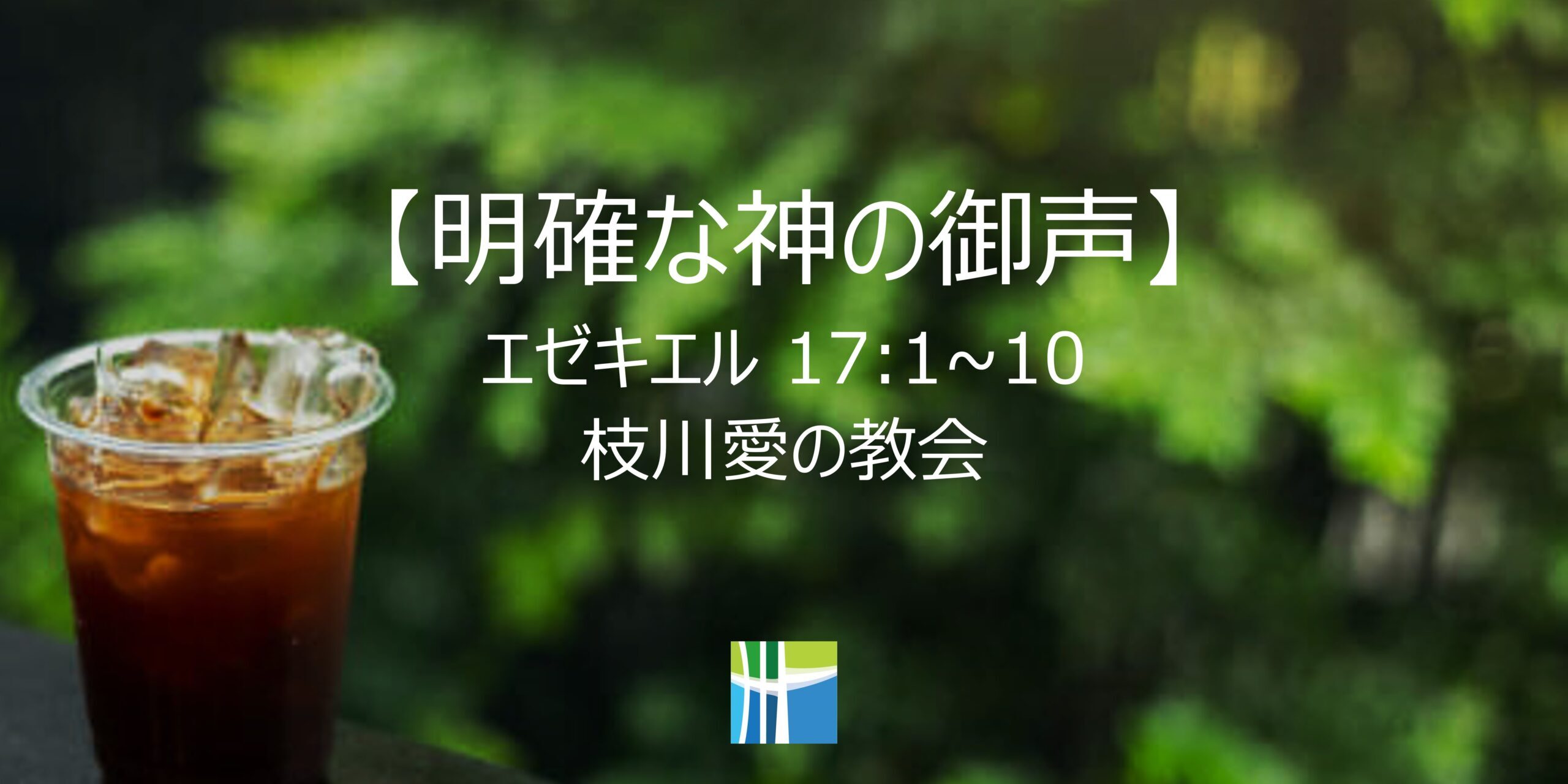エゼキエル 17:1~10
17:1 次のような主のことばが私にあった。
17:2 「人の子よ。イスラエルの家に謎をかけ、たとえを語れ。
17:3 『神である主はこう言われる。大きな翼、長い羽、色とりどりの豊かな羽毛の大鷲が、レバノンに飛んで来て、杉のこずえを取り去り、
17:4 その若枝の先を摘み取り、それをカナンの地へ運び、商人の町に置いた。
17:5 また、その地の種も取って来て、肥えた土地に植え、豊かな水のそばに柳のように植えた。
17:6 それは生長し、丈は低いが、よく生い茂るぶどうの木となった。その枝は鷲の方に向き、根は鷲の下に張り、こうして、ぶどうの木となって、枝を作り、若枝を出した。
17:7 さて、大きな翼と豊かな羽毛を持つもう一羽の大鷲がいた。すると、このぶどうの木は、潤いを得るために根をその鷲の方に向けて伸ばし、その枝を、自分が植わっているところからその鷲の方に伸ばした。
17:8 このぶどうの木は、枝を伸ばし、実を結んで見事なぶどうの木となるように、水の豊かな良い地に植えられていた。』
17:9 言え。『神である主はこう言われる。それはうまく育つであろうか。その根は抜き取られ、その実は摘み取られ、芽の付いた若枝はことごとく枯れないだろうか。それは枯れる。それを根こそぎ引き抜くのに、大きな力や多くの人々を必要としない。
17:10 見よ。それは植えられたが、うまく育つだろうか。東風がそれに吹きつけると、すっかり枯れてしまわないだろうか。その芽を出した苗床で、それは枯れてしまう。』」
本文は、バビロンとエジプトという大国に挟まれたイスラエルの緊迫した国際情勢を比喩した啓示である。近東は、エジプトが衰退し、バビロンが支配する秩序へと再編されるだろう。ゆえに、イスラエル最後の王ゼデキヤの責任は重大であった。しかしゼデキヤは、同盟国であるエジプトとの間で右往左往した。大義や義理を考えたのかもしれないが、それ以上に重要な「民の命」という優先順位を守ることができなかった。
神はエレミヤとエゼキエルを通して、バビロンを刺激してはならないというメッセージを繰り返し与えられた。それは「誰が味方か」という陣営選択の問題ではない。ゼデキヤは、最優先で民を生かす道を探さなければならなかった。神の御心は、国際情勢の判断や政治的分析の上に、神の啓示と御言葉によって養われた識別力を通して聞こえる。バビロンに仕えよと仰せられたのは敗北主義ではなく、一人でも多くの民を救うための道であった。
その時、近東のゼデキヤは地の変化を読み取ることができなかった。別の時代、極東の半島でも同じことがあった。明から清へ、清から日本帝国へと秩序が再編されるたびに、守旧派は事大の観念に囚われていた。義理や伝統、感情や人脈に縛られ、民がより多く死なねばならない道を選んだ。それが不従順であり、背信である。民を生かす道こそが従順であり、信仰である。
信仰があると言いながらも、命に対する責任と良心がなく、救わねばならないという使命がないなら、それは信仰ではなかったことの証明である。ゼデキヤが滅んだのは政治的判断を誤ったからではなく、民を救うべき良心と使命に目を閉じたからであり、その結果として目をえぐられたのだ。神の御声を聞くということは、神の心にかなった思いを抱くことであり、現実を認識する土台の上に良心と使命が生きているとき、神の御声は聞こえるのである。