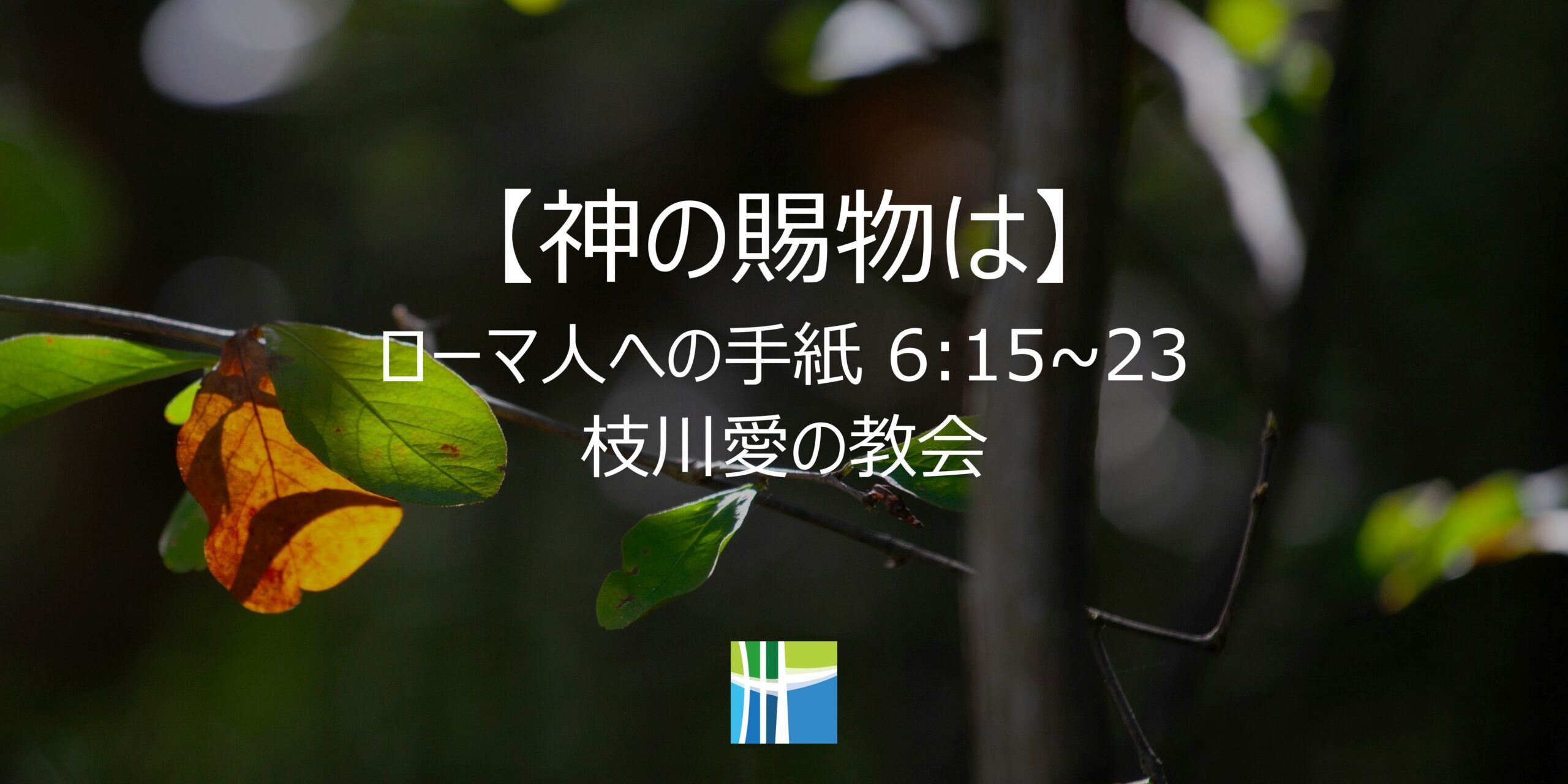ローマ人への手紙 6:15~23
6:15 では、どうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく、恵みの下にあるのだから、罪を犯そう、となるのでしょうか。決してそんなことはありません。
6:16 あなたがたは知らないのですか。あなたがたが自分自身を奴隷として献げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり、罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。
6:17 神に感謝します。あなたがたは、かつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、
6:18 罪から解放されて、義の奴隷となりました。
6:19 あなたがたの肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。以前あなたがたは、自分の手足を汚れと不法の奴隷として献げて、不法に進みました。同じように、今はその手足を義の奴隷として献げて、聖潔に進みなさい。
6:20 あなたがたは、罪の奴隷であったとき、義については自由にふるまっていました。
6:21 ではそのころ、あなたがたはどんな実を得ましたか。今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。
6:22 しかし今は、罪から解放されて神の奴隷となり、聖潔に至る実を得ています。その行き着くところは永遠のいのちです。
6:23 罪の報酬は死です。しかし神の賜物は、私たちの主キリスト・イエスにある永遠のいのちです。
パウロはローマ人への手紙5章で、アダムとキリストを対比させて福音を説明した。アダムの罪の後、すべての人が罪の中に生まれ、死のもとに入ったように、イエス・キリストの十字架の贖いを信じるすべての人に義といのちが与えられた。人間はそれぞれ独立して善悪を選び、自らの救いを達成できる自律的な存在ではない。善を行いたいと願ってもそのとおりにできず、悪を避けようと思っても避けられない。これは単なる意志の問題ではない。人間は望むと望まざるとにかかわらず、アダムとキリストという代表のもとに属する存在であるという意味である。神がいないと言い信じる人はどこにでもいるが、自らその枠組みの外に出ることができる人は誰もいない。
パウロは「罪が増し加わったところには、恵みもますます満ちあふれました」(ローマ5:20)と言った。これは福音の偉大な宣言だが、一方で「罪を多く犯すほど恵みも多く受けられる」という誤解を招きかねない言葉でもある。しかしパウロの意図は、罪と恵みが量的に比例するということではない。むしろ、罪を深く自覚するほど、神の恵みをより深く知るようになるという意味である。パウロはこの誤解を正すために、洗礼の意味を持ち出す。洗礼とはイエス・キリストの死と復活に結びつけられる出来事である。すなわち、洗礼を受けた者は古い人がキリストとともに十字架につけられて罪に対して死に、よみがえられた主と結ばれて新しいいのちに生きるのである(ローマ6:3-5)。したがって、なお罪を犯し続け、それを正当化したり恵みによって合理化する人の口から出る「恵み」や「信仰」は、その真実性を疑わざるを得ない。
続いてパウロは、しもべと主人のたとえを用いて説明する。人間は決して中立的な存在ではなく、必ずある主人のもとに置かれている。分別のある人なら、人間が本来的に自立した存在ではなく、従属的であることに異を唱えられないだろう。罪に従えば罪のしもべとなり、神に従えば義のしもべとなる。世を好めば世のしもべとなり、みことばを好めば神のしもべとなる。これは避けられない帰結である。世の期待に従って生きながら口先で信仰を語っても、その中身は空虚である。世の忙しい歩みを止め、神の前に立ち止まる勇気がなければ、信仰は居場所を失い、消えていく。真実な信仰であるならば、立ち止まり、問い、従うことが必ず伴う。
いわゆる「ただで受けた恵み」に頼って、緊張感なく罪を重ねて生きることはできない。パウロが語る恵みとは、新しい主人に仕える力であり、真の自由を得る力である。その人の生き方が恵みの実在を証明する。完全であるという意味ではない。人は依然として不完全である。しかし、敬虔な時も、失敗してつまずく時も、良心はそれを映し出す。パウロはこう結論する。
「罪の報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、私たちの主キリスト・イエスにある永遠のいのちです。」ローマ6:23 恵みとは罪の言い訳ではなく、永遠のいのち、すなわち救われた聖徒の生へと導く力である。