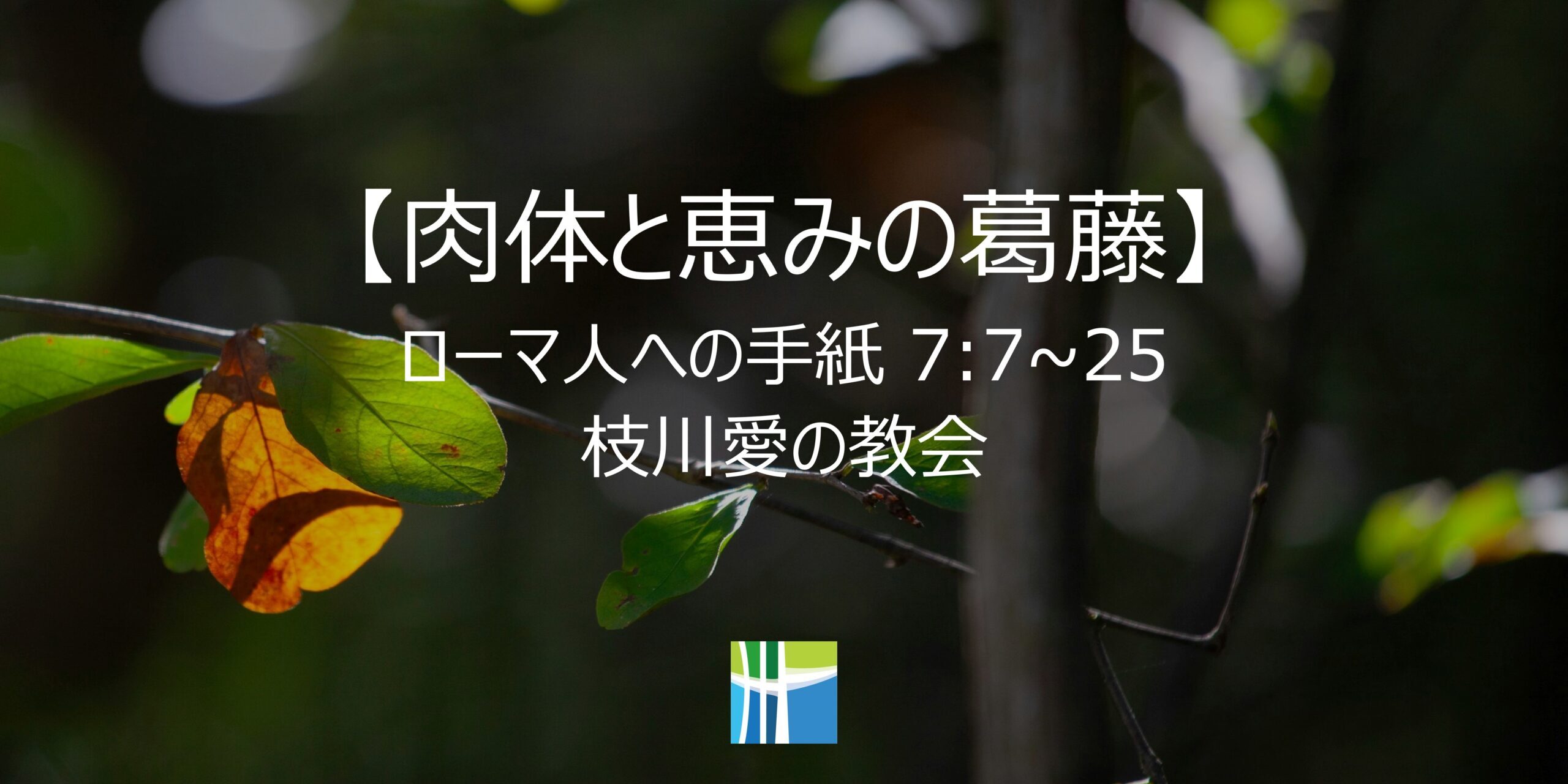ローマ人への手紙 7:7~25
7:7 それでは、どのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ、律法によらなければ、私は罪を知ることはなかったでしょう。実際、律法が「隣人のものを欲してはならない」と言わなければ、私は欲望を知らなかったでしょう。
7:8 しかし、罪は戒めによって機会をとらえ、私のうちにあらゆる欲望を引き起こしました。律法がなければ、罪は死んだものです。
7:9 私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来たとき、罪は生き、
7:10 私は死にました。それで、いのちに導くはずの戒めが、死に導くものであると分かりました。
7:11 罪は戒めによって機会をとらえ、私を欺き、戒めによって私を殺したのです。
7:12 ですから、律法は聖なるものです。また戒めも聖なるものであり、正しく、また良いものです。
7:13 それでは、この良いものが、私に死をもたらしたのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ、罪がそれをもたらしたのです。罪は、この良いもので私に死をもたらすことによって、罪として明らかにされました。罪は戒めによって、限りなく罪深いものとなりました。
7:14 私たちは、律法が霊的なものであることを知っています。しかし、私は肉的な者であり、売り渡されて罪の下にある者です。
7:15 私には、自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。
7:16 自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。
7:17 ですから、今それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。
7:18 私は、自分のうちに、すなわち、自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに、実行できないからです。
7:19 私は、したいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。
7:20 私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。
7:21 そういうわけで、善を行いたいと願っている、その私に悪が存在するという原理を、私は見出します。
7:22 私は、内なる人としては、神の律法を喜んでいますが、
7:23 私のからだには異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を、からだにある罪の律法のうちにとりこにしていることが分かるのです。
7:24 私は本当にみじめな人間です。だれがこの死のからだから、私を救い出してくれるのでしょうか。
7:25 私たちの主イエス・キリストを通して、神に感謝します。こうして、この私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。
パウロは第6章で、キリストと結ばれて罪に対して死に、新しいいのちの中を生きる生活について語った。しかし第7章では、罪の執拗さゆえに、聖徒の内的矛盾が依然として存在することを告白した。信仰によって義とされたとはいえ、この地上に生きている間は、罪の律法と神の律法との間の葛藤は消え去らないというのである。この主題を読むには、正直でなければならない。信仰の確信を求められた人々は、この自己矛盾を認める勇気を持つことができなかった。
律法自体は悪いものではなかった。ただ罪が律法を利用して聖徒を欺いただけである。問題の根源は律法ではなく罪にある。だからこそパウロは、善を願いながらも悪を行ってしまうという自己矛盾を暴露したのだ。心では神の律法に従おうとしながらも、体は罪の律法に引きずられてしまう、その矛盾の極みにおいて「わたしは本当にみじめな人間です」と叫んだ。これはパウロ個人の道徳的葛藤の告白ではなく、人間存在の実相を告発したのである。
絶望と希望は隣り合わせにある。「救い」とは、絶望を知るということだ。絶望を知らなければ「救い」という言葉は成立しない。したがってパウロの絶叫と告白に共感する者にとって、その絶望はやがて感謝へと変わる。「わたしたちの主イエス・キリストを通して神に感謝します」。律法も悪くなく、自分自身も大切な存在である。聖徒の実存とは、肉と恵みの間の葛藤の中であきらめずに福音を握りしめる生活である。私たちはこの緊張の中で、救いをもたらす福音を見出しつつ生きるのである。