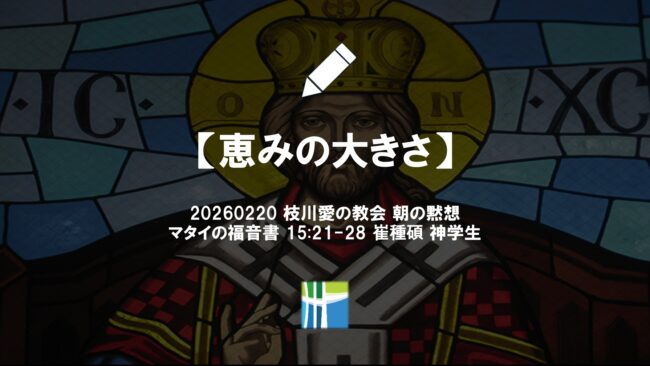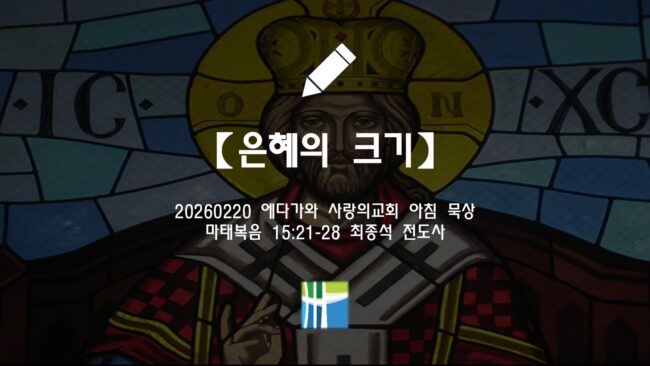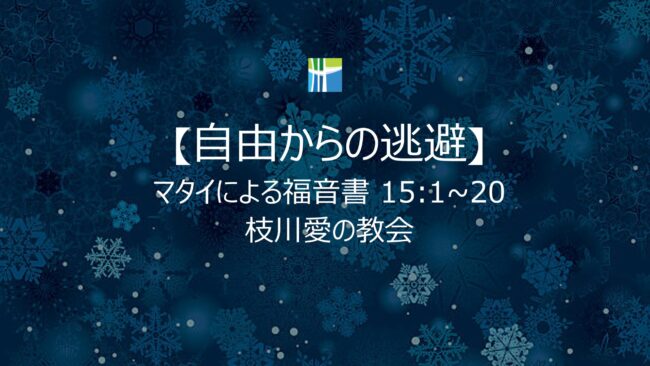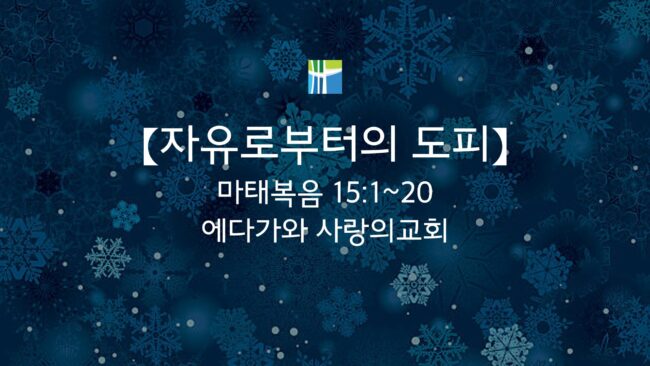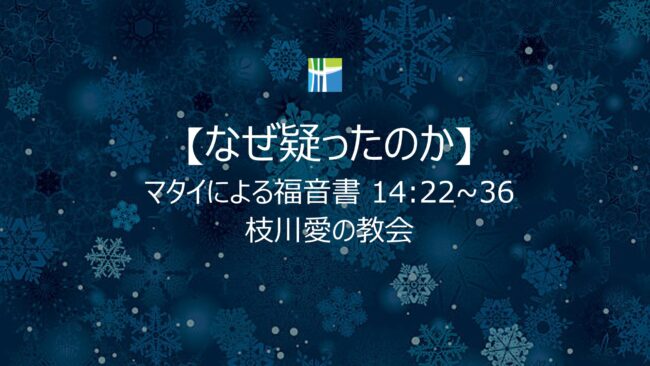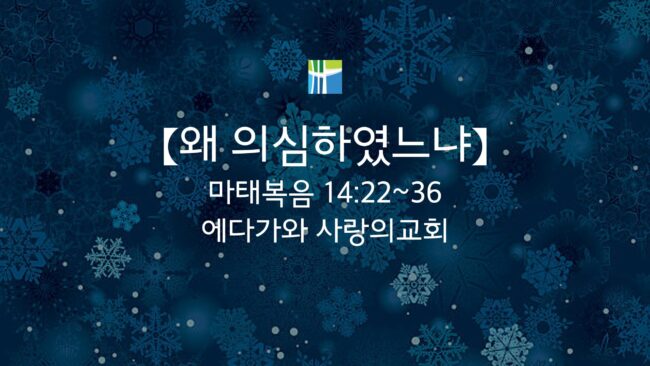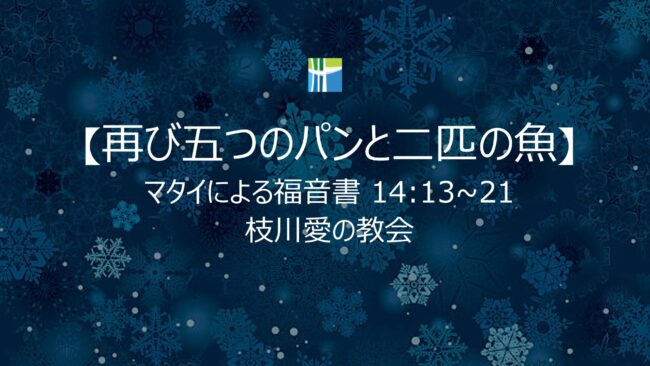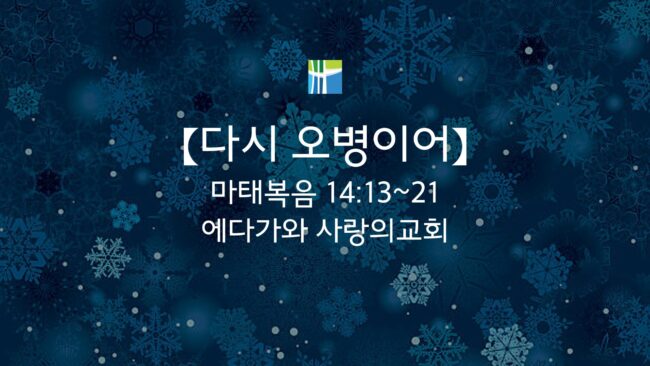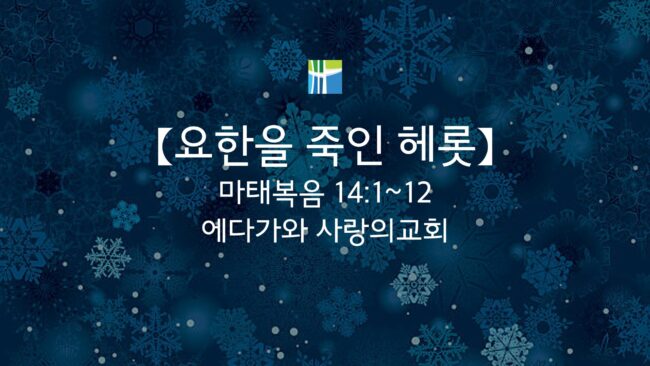マタイの福音書 黙想【恵みの大きさ】20260220(金) 枝川愛の教会 崔種碩 神学生
マタイの福音書 15:21-28 15:21 イエスはそこを去ってツロとシドンの地方に退かれた。 15:22 すると見よ。その地方のカナン人の女が出て来て、「主よ、ダビデの子よ。私をあわれんでください。娘が悪霊につかれて、ひどく苦しんでいます」と言って叫び続けた。 15:23 しかし、イエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちはみもとに来て、イエスに願った。「あの女を去らせてください。後について来て叫んでいます。」 15:24 イエスは答えられた。「わたしは、イスラエルの家の失われた羊たち以外のところには、遣わされていません。」 15:25 しかし彼女は来て、イエスの前にひれ伏して言った。「主よ、私をお助けください。」 15:26 すると、イエスは答えられた。「子どもたちのパンを取り上げて、小犬に投げてやるのは良くないことです。」 15:27 しかし、彼女は言った。「主よ、そのとおりです。ただ、小犬でも主人の食卓から落ちるパン屑はいただきます。」 15:28 そのとき、イエスは彼女に答えられた。「女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願うとおりになるように。」彼女の娘は、すぐに癒やされた。 今日の箇所に記されている出来事は、色々な意味で、有名な箇所です。ある人は、イエス様がカナン人の女に語られた言葉を見て、イエス様が人を差別されたのかと言い、ある人は、それは彼女の信仰を試すためであったのだと解釈します。実際のところ、どちらが正しいか知っておられるのは、その言葉を語られたイエス様ご自身だけでしょう。 しかし、イエス様の言葉に対する彼女の応答を見るとき、なぜこの出来事が私たちの聖書に記されたのか、その理由ははっきりと見えてきます。カナン人の女の姿と、その言葉は、直前の箇所でイエス様と対立していたパリサイ人や律法学者たちの姿と、はっきりと対照されています。 彼らは、自分たちと、自分たちが守ってきた伝統が尊重されることを求めました。それが神様のみことばに反するものであったにもかかわらずです。イエス様が「口から出るものは心から出る」と語られたとおり、彼らの内側には、神様のみことばよりも自分自身を高く位置付ける傲慢さがあったのです。 しかし、今日の箇所のカナン人の女の口から出た言葉は、まったく異なるものでした。彼女は、自分が尊重されることを少しも求めていませんでした。異邦人として軽視され、犬のように扱われたとしても、それでもなおイエス様の恵みにあずかりたいという、堅い決意がそこにはありました。彼女にとって、自分が高められることや尊重されることは、神様の御前では何の意味もなかったのです。 イエス様なら、パン屑のような恵みでも娘を癒やすことができると信じた彼女の信仰を「立派だ」と言われたことは、確かに重要です。しかし同時に、その恵みをいただくためなら、自分がどのように扱われるとしても構わないという、へりくだった姿勢、パリサイ人や律法学者とは正反対の姿勢を、イエス様が尊いものとされたことを忘れてはいけません。 カナン人の女にとって、神様の恵みはそれほどまでに大きなものでした。自分のすべてをかけてでも、何をしてでも得なければならないものであったのです。しかし、パリサイ人や律法学者にとっては、自分たちの守ってきた伝統とその尊重こそが、神様の恵みと引き換えにしてでも守るべきものになっていたのです。 私たちにおいて、神様の恵みはどのようなものでしょうか。カナン人の女の信仰のように、他の何ものとも引き換えられない、すべてを失ってでも得なければならないものであることを、私たちは忘れてはいないでしょうか。今一度、自らの心を省みましょう。 https://youtu.be/_q8QUYxphWs?si=lkpAHDoRMqI20fhU