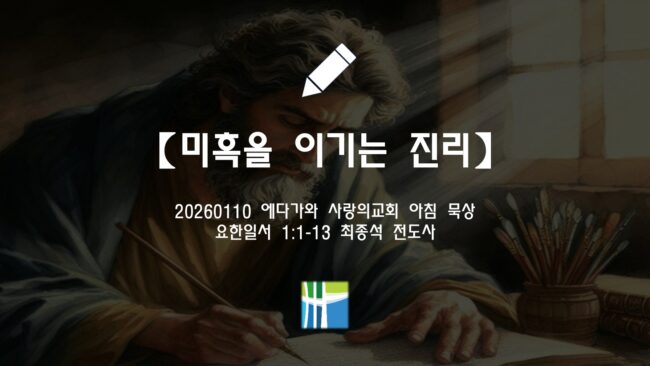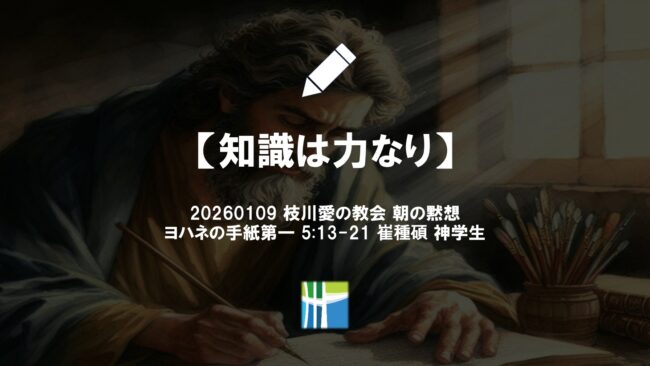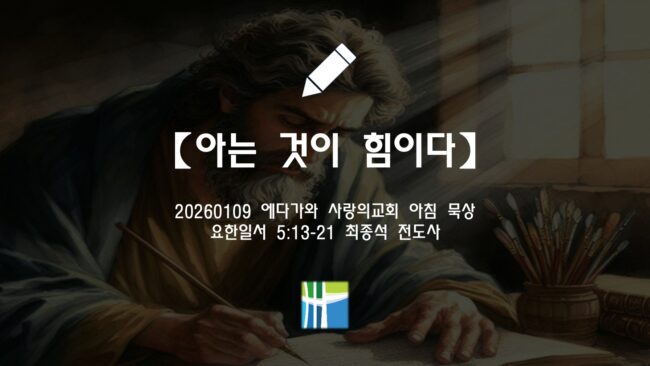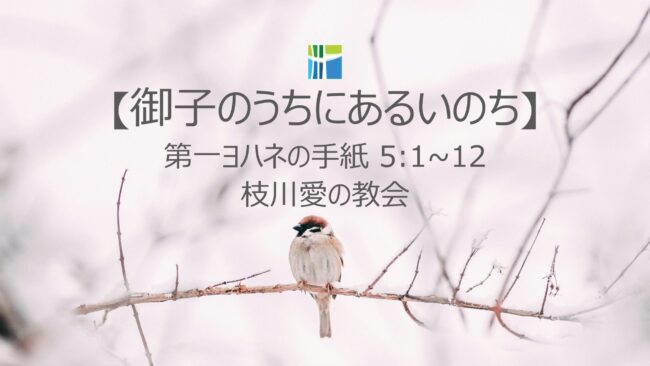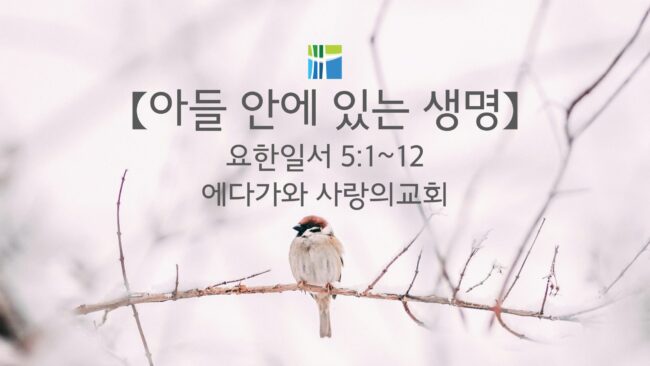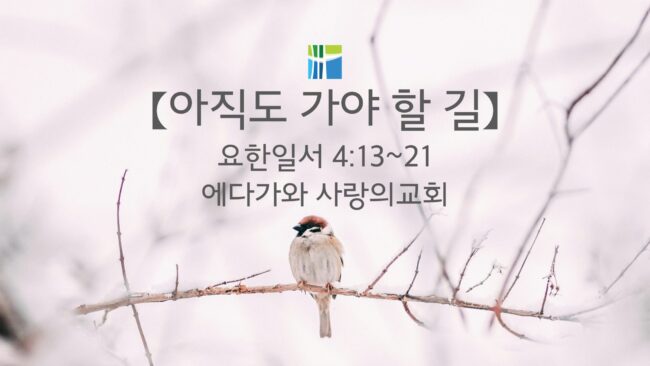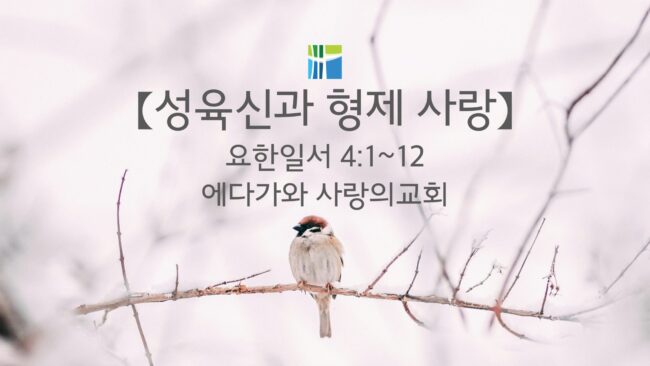ヨハネの手紙第二 黙想【惑わされない真理】20260110(土) 枝川愛の教会 崔種碩 神学生
ヨハネの手紙第二 1:1-13 1:1 長老から、選ばれた婦人とその子どもたちへ。私はあなたがたを本当に愛しています。私だけでなく、真理を知っている人々はみな、愛しています。 1:2 真理は私たちのうちにとどまり、いつまでも私たちとともにあるからです。 1:3 父なる神と、その御父の子イエス・キリストから、恵みとあわれみと平安が、真理と愛のうちに、私たちとともにありますように。 1:4 御父から私たちが受けた命令のとおりに、真理のうちを歩んでいる人たちが、あなたの子どもたちの中にいるのを知って、私は大いに喜んでいます。 1:5 そこで婦人よ、今あなたにお願いします。それは、新しい命令としてあなたに書くのではなく、私たちが初めから持っていた命令です。私たちは互いに愛し合いましょう。 1:6 私たちが御父の命令にしたがって歩むこと、それが愛です。あなたがたが初めから聞いているように、愛のうちを歩むこと、それが命令です。 1:7 こう命じるのは、人を惑わす者たち、イエス・キリストが人となって来られたことを告白しない者たちが、大勢世に出て来たからです。こういう者は惑わす者であり、反キリストです。 1:8 気をつけて、私たちが労して得たものを失わないように、むしろ豊かな報いを受けられるようにしなさい。 1:9 だれでも、「先を行って」キリストの教えにとどまらない者は、神を持っていません。その教えにとどまる者こそ、御父も御子も持っています。 1:10 あなたがたのところに来る人で、この教えを携えていない者は、家に受け入れてはいけません。あいさつのことばをかけてもいけません。 1:11 そういう人にあいさつすれば、その悪い行いをともにすることになります。 1:12 あなたがたにはたくさん書くべきことがありますが、紙と墨ではしたくありません。私たちの喜びが満ちあふれるために、あなたがたのところに行って、直接話したいと思います。 1:13 選ばれたあなたの姉妹の子どもたちが、あなたによろしくと言っています。 ヨハネの第二の手紙は、一章、十三節で構成されている短い手紙です。しかし、その短さのゆえに、この手紙の目的と内容は、力強く、またはっきりと伝わってきます。 「愛の使徒」と呼ばれるヨハネは、今日の御言葉の中で、ヨハネらしく愛を強調すると同時に、反キリストたち、すなわち異端に対して、断固とした態度を取るように勧めています。しかし、その異端への対処は、決して愛を捨てることではなく、むしろ真の愛を守るためであることが、ここで示されています。 異端への対処の問題は、長い間、教会の中で議論されてきて、どの方法が正しいと言うことも難しい問題であります。単に彼らに対して厳しく対処することだけが正しいと言い切れないのは、敵を愛し、その相手にまでも真理を伝えることが、キリスト者の使命であるとも言えるからです。 聖書の中で反キリストと呼ばれる者たちには、いくつかの特徴があります。それは、真理を歪め、その歪められた真理に人々を惑わす、という点です。ヨハネは、彼らに惑わされないため、また、私たちが受ける豊かな報いを失わないために、自ら注意しなさいと勧めているのです。 私たちは、彼らに惑わされないため、また、彼らが歪めた真理に欺かれて真の真理を失わないために、私たちの中にある真理を、さらに確かなものとして築き上げていかなければなりません。そして、彼らがもはや私たちにとって危険とならなくなり、私たちの中に根づいた真の真理が、彼らの歪んだ真理を正し、彼らもまた、完全な報いにあずかることができるようになる、それこそが、最も望ましい道でしょう。 このような務めを一人で担うことは危険なことです。私たちはいつでも、「自分は惑わされない」という思い込みに陥る可能性もあり、実際に惑わされてしまうこともあるでしょう。だからこそ、この働きは、真の真理のうちに互いに愛し合う共同体とともに、その共同体を導いておられる聖霊様を通して、成し遂げられなければならないのです。 https://youtu.be/6-1NgGkmLC4?si=ysH7XbM-b2neW06S