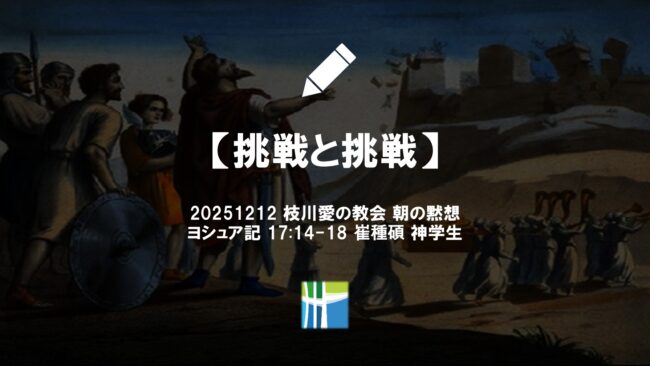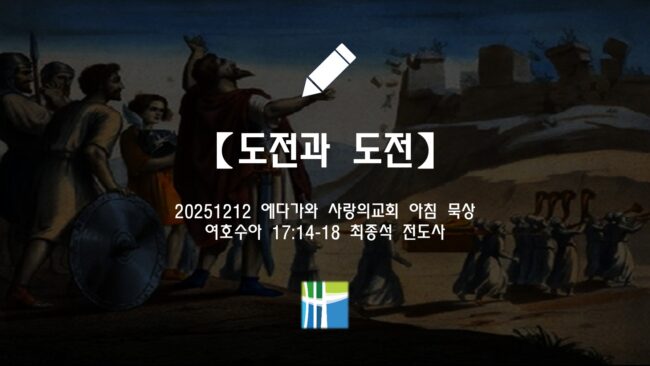ヨシュア 黙想 【ヨシュアとティムナテ・セラ】 20251216(火) 枝川愛の教会 趙鏞吉 牧師
ヨシュア 19:24~51 19:24 五番目のくじはアシェル部族の諸氏族に当たった。 19:25 彼らの地域はヘルカテ、ハリ、ベテン、アクシャフ、 19:26 アラメレク、アムアデ、ミシュアルである。西に向かってカルメルとシホル・リブナテに達し、 19:27 日の昇る方、すなわちベテ・ダゴンに戻り、ゼブルンに、さらに北の方でエフタフ・エルの谷に達し、ベテ・ハ・エメク、ネイエルを経て左の方、カブルに出て、 19:28 エブロン、レホブ、ハモン、カナを経て大シドンに至る。 19:29 その境界線はラマの方に戻り、城壁のある町ツロに至る。それから境界線はホサの方に戻る。その終わりは海である。マハレブ、アクジブ、 19:30 ウマ、アフェク、レホブ。二十二の町とその村々。 19:31 これがアシェル部族の諸氏族の相続地であり、その町々とそれらの村々である。 19:32 六番目のくじはナフタリ族に、すなわち、ナフタリ族の諸氏族に当たった。 19:33 彼らの地域は、ヘレフと、ツァアナニムの樫の木から、アダミ・ハ・ネケブ、ヤブネエルを経てラクムに至る。その終わりはヨルダン川である。 19:34 その境界線は西の方、すなわちアズノテ・タボルに戻り、そこからフコクに出て、南でゼブルンに達し、西でアシェルに達し、日の昇る方のヨルダン川でユダに達する。 19:35 城壁のある町はツィディム、ツェル、ハマテ、ラカテ、キネレテ、 19:36 アダマ、ラマ、ハツォル、 19:37 ケデシュ、エデレイ、エン・ハツォル、 19:38 イルオン、ミグダル・エル、ホレム、ベテ・アナト、ベテ・シェメシュ。十九の町とその村々。 19:39 これがナフタリ部族の諸氏族の相続地であり、その町々とそれらの村々である。 19:40 七番目のくじはダン部族の諸氏族に当たった。 19:41 彼らの相続地の領域はツォルア、エシュタオル、イル・シェメシュ、 19:42 シャアラビン、アヤロン、イテラ、 19:43 エロン、ティムナ、エクロン、 19:44 エルテケ、ギベトン、バアラテ、 19:45 エフデ、ベネ・ベラク、ガテ・リンモン、 19:46 メ・ハ・ヤルコン、ラコン、およびヤッファに面する地域である。 19:47 ダン族の地域は彼らから失われたので、ダン族は上って行き、レシェムと戦った。彼らはそこを取り、剣の刃で討つと、これを占領してそこに住み、自分たちの先祖ダンの名にちなんでレシェムをダンと呼んだ。 19:48 これがダン部族の諸氏族の相続地であり、その町々とそれらの村々である。 19:49 地を地域ごとに相続地として割り当て終えたとき、イスラエルの子らは、自分たちの間に一つの相続地をヌンの子ヨシュアに与えた。 19:50…