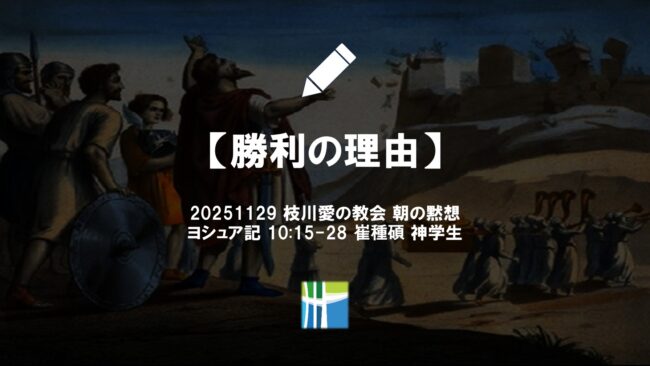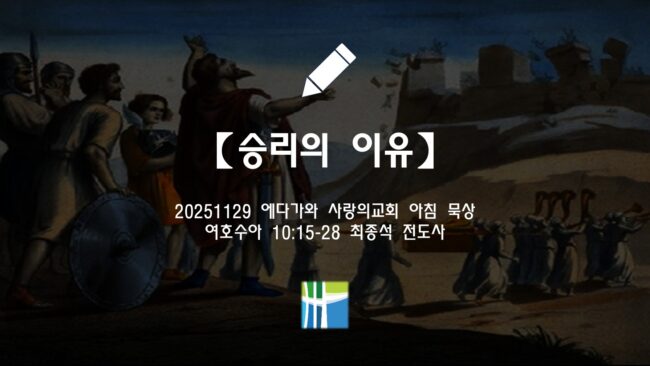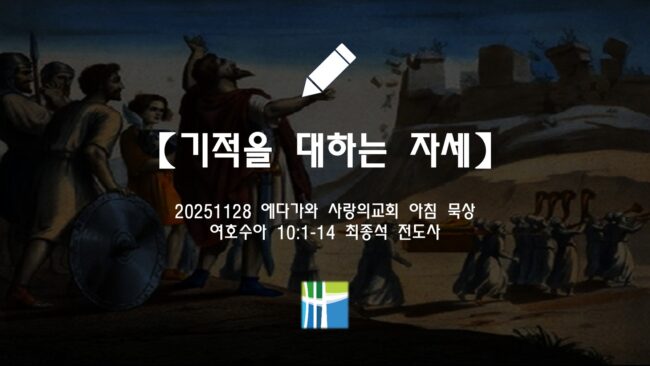ヨシュア 黙想 【欲望というアキレス腱を断ち切れ】 20251201(月) 枝川愛の教会 趙鏞吉 牧師
ヨシュア 11:1~15 11:1 ハツォルの王ヤビンはこのことを聞いて、マドンの王ヨバブ、シムロンの王、アクシャフの王、 11:2 また、北方の山地、キネレテの南のアラバ、シェフェラ、西方のドルの高地の王たち、 11:3 すなわち、東西のカナン人、アモリ人、ヒッタイト人、ペリジ人、山地のエブス人、ヘルモンのふもと、ミツパの地のヒビ人に人を遣わした。 11:4 彼らはその全陣営とともに出て来た。海辺の砂のように大勢の兵で、馬や戦車も非常に多かった。 11:5 これらの王たちはみな集まり、進んで行き、イスラエルと戦うためにメロムの水のほとりでともに陣を敷いた。 11:6 主はヨシュアに告げられた。「彼らを恐れてはならない。明日の今ごろ、わたしは彼らをことごとく、イスラエルの前で刺し殺された者とするからだ。あなたは彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼け。」 11:7 ヨシュアはすべての戦う民とともに、メロムの水のほとりにいる彼らを急襲した。 11:8 主は彼らをイスラエルの手に渡された。イスラエルは彼らを討ち、大シドンおよびミスレフォト・マイムまで、東の方ではミツパの谷まで彼らを追い、一人も残さず討った。 11:9 ヨシュアは主が告げられたとおりに彼らにした。彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼いた。 11:10 ヨシュアはそのとき引き返して、ハツォルを攻め取った。その王は剣で討った。ハツォルは当時、これらすべての王国の盟主だったからである。 11:11 ヨシュアたちはそこにいたすべてのものを剣の刃で討ち、聖絶した。息のある者は一人も残らなかった。彼はハツォルを火で焼いた。 11:12 ヨシュアは、これらの王たちのすべての町を攻め取り、そのすべての王たちを剣の刃で討ち、聖絶した。主のしもべモーセが命じたとおりであった。 11:13 イスラエルは、丘の上に立っている町々はどれも焼かなかった。ただし、ヨシュアは例外としてハツォルだけは焼いた。 11:14 これらの町々のすべての分捕り物と家畜を、イスラエルの子らは戦利品として自分たちのものとした。人間だけはみな剣の刃で討ち、根絶やしにした。息のある者は一人も残さなかった。 11:15 主がそのしもべモーセに命じられたとおりに、モーセはヨシュアに命じ、ヨシュアはそのとおりに行った。主がモーセに命じられたすべてのことばを、彼は一言も省かなかった。 失敗の中でも柔軟さを保つことができるなら、成功よりも大きな学びを得ることができる。イスラエルはアイの敗北を通して、世に対してはより堅くなり、神に対してはより完全な従順を学んだ。強い指導者とは、一度も失敗しなかった人ではなく、失敗を通して自分を省み、構造を立て直すことのできる人である。アイの出来事は、イスラエルとヨシュアにそのような「霊的弾力」を育てる契機となった。 神は失敗を通して謙遜を教え、謙遜を通して従順を教え、そして従順する人を通してより大きな働きを委ねられる。だからこそ、回復したイスラエルに神は北方の連合軍を打てと命じられた。ハツォル王ヤビンが率いるその連合軍は当時最強の軍事力を持っていたが、神は彼らを恐れるなと言われた。失敗の場所で従順を学んだ者こそ、この言葉が持つ力を理解し、受け入れることができるのだ。 ヨシュアは神の言葉を戦略とし、命じられたすべてを一つも欠けることなく、そのまま実行した。すでに勝利が確定している戦いで、敵の馬のアキレス腱を断ち切ることは決して容易な従順ではなかった。なぜなら、馬と戦車は当時の最先端の軍事システムだったからである。もともと北方連合軍が強大に見えた理由もまさにそこにあった。しかしイスラエルは戦利品に欲を出さず、神の言葉通りに完全に従った。だからこそ勝利は完全なものとなった。 人間は完全になれず、戦略も完璧でありえない。しかし、自分の思いを手放すことができるなら、完全に従順することはできる。そしてその従順は神の御心を映し出すゆえに、人間の不完全な結果ではなく、神の完全な結果として現れる。従順が戦略となるとは、神の言葉が人間の計算より先にあるという事実を知るだけでなく、その秩序を実際の生活、実際の戦い、実際の決断の場に適用するということである。従順は観念ではない。自分を捨てて神に従う従順こそ、その現場において力となり、勝利となる。神の前に従うとき、そこには不純物は残らない。