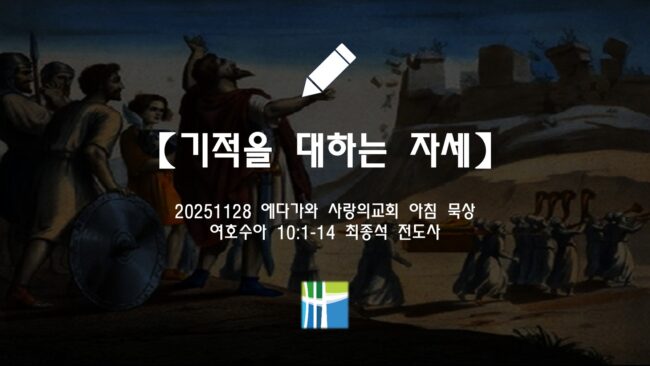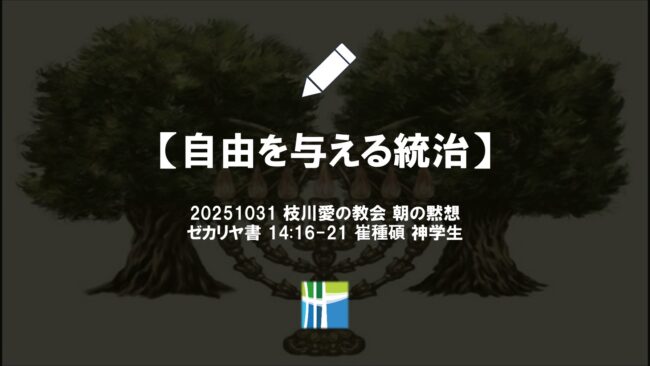ヨシュア 9:1~15 9:1 さて、ヨルダン川の西側の山地、シェフェラ、レバノンに至る大海の全沿岸のヒッタイト人、アモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の王たちはみな、これを聞くと、 9:2 ともに集まり、一つになってヨシュアおよびイスラエルと戦おうとした。 9:3 ギブオンの住民たちは、ヨシュアがエリコとアイに対して行ったことを聞くと、 9:4 彼らもまた策略をめぐらし、変装をした。古びた袋と、古びて破れて継ぎ当てをしたぶどう酒の皮袋をろばに負わせ、 9:5 繕った古い履き物を足にはき、古びた上着を身に着けた。彼らの食糧のパンはみな乾いて、ぼろぼろになっていた。 9:6 彼らはギルガルの陣営のヨシュアのところに来て、彼とイスラエルの人々に言った。「私たちは遠い国から参りました。ですから今、私たちと盟約を結んでください。」 9:7 イスラエルの子らはそのヒビ人たちに言った。「おそらく、あなたがたは、私たちのただ中に住んでいるのだろう。どうして私たちがあなたがたと盟約を結べるだろうか。」 9:8 彼らはヨシュアに言った。「私たちは、あなたのしもべです。」ヨシュアは彼らに言った。「あなたがたは何者か。どこから来たのか。」 9:9 彼らは彼に言った。「しもべどもは、あなたの神、主の名のゆえにとても遠い国から参りました。主のうわさ、および主がエジプトで行われたすべてのこと、 9:10 主がヨルダンの川向こうのアモリ人の二人の王、ヘシュボンの王シホン、およびアシュタロテにいたバシャンの王オグになさった、すべてのことを聞いたからです。 9:11 私たちの長老や、私たちの国の住民はみな私たちに言いました。『旅のための食糧を手にして彼らに会いに出かけなさい。そして彼らに、「私たちは、あなたがたのしもべです。今、どうか私たちと盟約を結んでください」と言いなさい。』 9:12 これが私たちのパンです。私たちがあなたがたのところに来ようと出た日、それぞれ自分の家で食糧として準備したときには、まだ温かかったのですが、今はご覧のとおり、干からびて、ぼろぼろになってしまいました。 9:13 これがぶどう酒の皮袋です。私たちがこれらを満たしたときには新しかったのですが、ご覧のとおり破れてしまいました。これが私たちの上着と私たちの履き物です。とても長い旅のため古びてしまいました。」 9:14 そこで人々は彼らの食糧の一部を受け取った。しかし、主の指示を求めなかった。 9:15 ヨシュアは彼らと和を講じ、彼らを生かしておく盟約を結んだ。会衆の上に立つ族長たちは彼らに誓った。 エリコの城とアイの町が崩れ落ちると、残されたカナンの諸部族は恐れを感じ、連合してイスラエルと戦うことを決意した。しかし、ギブオンだけは別の道を選んだ。彼らは自らを欺きながら、イスラエルのしもべになることを申し出たのである。そうすれば、滅ぼし尽くされることを免れ得ると考えたからであろう。それはギブオンにとっても、イスラエルにとっても、合理的で魅力的な条件であった。ギブオンの立場からすれば生き延びることができ、イスラエルの側からすれば、戦わずして勝利を得るだけでなく、現地の部族をしもべとして従わせることができたからである。 しかし本文は、「彼らは主の御心を求めなかった」(14節)という言葉によって、この事件の本質を伝えている。すなわち、彼らの判断と選択に誤りがあったことを示しているのである。イスラエルは神に何を問うべきであったのだろうか。ギブオンをしもべとすべきか、それとも拒むべきか、と問うべきだったのだろうか。「主に問わなかった」とは、すべてのことを漏れなく神に祈った後でなければ決断してはならない、という意味なのだろうか。 イスラエルにはすでに、「カナンの諸族をことごとく滅ぼせ」という神の上位命令が与えられていたではないか。その命令は性質上、例外を許さない絶対的なものであった。イスラエルには、カナンの民の中から誰かをしもべとすることも、彼らと共存することも許されていなかった。なぜ彼らを滅ぼさねばならなかったのかという問いは、今日の主題ではないが、それは不純なものの影響力を完全に排除し、新しいものへの再生を象徴する行為として理解できるであろう。 「神に問わなかった」というのは、祈る行為を怠ったという意味ではない。イスラエルはそれなりに慎重であり、悩み、最善を尽くして合理的な判断を下したはずである。問題はその「合理性」にあった。彼らはすでに与えられていた神の命令を基準とせず、状況に応じた合理的判断を優先したのである。こうして彼らは、神の上位命令を自分たちの判断で勝手に調整してしまった。 しかし、この種の合理性はやがて妥協となり、不従順となる。問題は慈悲にあったのではなく、命令を自分なりの基準で再解釈したことにあった。聖書は、それこそが神の御心から逸脱することであると厳しく警告している。神が自分を導いておられる方向をすでに知っていながら、状況の合理性に従うことは、神の方向に逆らうことであり、妥協することであり、それこそが「神に問わなかった」こととなる。祈りという行為をしなかったのではなく、なお自分自身の方向設定が明確でなかったことに問題があったのである。